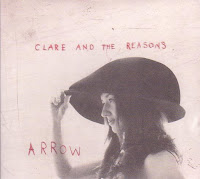久しぶりにブログを再開することにしました。しばらくiTunesに音楽を整理するのに時間をとられていましたが、それも一段落したので少しずつブログを書いてみることにしました。
で、復帰第一回は、初めて買ったCDを載せることにしました。このCDが発売された頃はレコードよりもCDが主流になった時期でした。私はCD化せずにレコードに拘っていたのですが、このアルバムがCDしか発売されなかったので、このCDを買うのに併せてCDプレーヤーを買ったのでした。今でも、渋谷の宇田川町の現在の
イエロー・ポップの隣にあったCISCOで購入したのを覚えています。
さて、この作品はHatfields and the NorthやNational Healthなどで超ハイセンスな演奏を聴かせくれるキーボード奏者と、Spirogyraで美しい歌唱を聴かせてくれるヴォーカリストとのユニットであります。BarbaraはHatfields and the Northのコーラス・パートを担当するNorthettesのメンバーでもあります。
で、このユニットの音楽は、カンタベリー系のプログレ~ジャズ・ロックの流れと異なるスーパー・ポップな内容であります。しかも、他に例の無いワン・アンド・オンリーな音楽であります。iPodを使うようになって最初の頃はひたすらシャッフルを使っていましたが、このアルバムはシャッフルするよりも(もちろん一曲毎のクオリティも高いのですが)この曲順で聴くのが最も宜しいようです。

MIDI Inc.からリリースされている日本編集版は曲目が異なります。オリジナルの曲目、曲順は↓で参照できます。