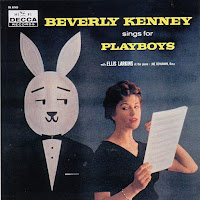Kittyが亡くなる一年程前、エニスのコンサートホールGlórなどでのライブ音源を収録した作品。Martin Hayes & Dennis Cahillの他、ブズーキのEoin O'NeillやコンサティーナのDympna O'Sullivanさん、アコーディオンのJosephine Marshさんなどのサポートを得て、溌剌とした演奏が収められています。
下のビデオは、2002年、丁度私がWillie Clancy Summer Scoolに参加した年の映像です。Willie Clancyでは毎晩楽器毎のリサイタルが開催されるのですが、Kittyさんもコンサティーナ・リサイタルに出演していました。お洒落な青いスーツで決めていらっしゃいました。下のビデオも他のメンバーがヨレた服装なのに一人だけオシャレです。