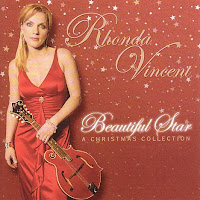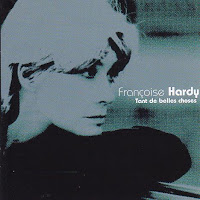ルイジアナ, ニューオリンズのアーティストによるクリスマス・ソング集。お祭り好きな土地柄かクリスマス・アルバムが沢山あるようです。私も何枚か持っていますが、このアルバムが一番のお気に入りです。中でもAaron Nevilleの"The Christmas Song (Chestnuts Roasting On An Open Fire)"とIrma Thomasの"O Holy Night"が最高です。The Dixie Cupsの"Let it snow"やAlen Toussaintの"White Christmas"も良いですね。Johnny Vidacovichの独特のドラミングも活躍するのも楽しいです。
Aaronのクリスマス・ソングはかなり沢山あります。"The Christmas Song"もいくつかのバージョンがあるようですが、上記のアルバムのものが一番気に入っています。また、"The Christmas Song"は、本家のNet King Coleをはじめ、Natalie Cole、竹内まりあ、Linda Ronstadtなどなど多くの人のバージョンがありますが、それらの中でも、このアルバムのAaronのものが最高のように思います。